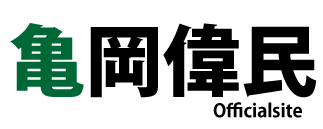くわごを一粒、口に含んで高夫は国会に出かけていった。―こころのふるさと・伊達―
阿佐ヶ谷の、高夫の玄関のわきには、一本の桑の木があった。高夫が自ら植えて大切に育てていたものである。普通、玄関わきといえば、松や楓を植えてそうなものだが、高夫は桑の木を植えた。
夏になると、桑は緑の小さな身をいっぱいつけた。「おお、くわごがなた…。」高夫は毎朝、出がけに桑の実を見るのを楽しみにしていた。くわごは、緑からだんだんオレンジ色になり、鮮やかな赤になった。「だめだめ。これは黒くならないと食べられないんだ。」-珍しがって食べたがる子供たちに言いきかせる高夫自身も、その時ばかりは子供のような笑顔を見せた。
秋が来ると、くわごは紫になり、やがて黒くなった。触れれば今にも汁が出そうに熟れて、つやつやと輝いている。「ほら、くわごができたぞ。」高夫はうれしそうに、家族のひとりひとりに一粒ずつくわごを配り、自分も口に含んだ。「どうだ、うまいだろう。」甘ずっぱいくわごの味が口中にひろがる。子供たちも高夫も、口のまわりをくわごの汁で真赤に染めてにこにこしていた。
高夫の故郷・伊達は、養蚕の盛んな村だった。あちこちにつややかな緑の桑畑が広がり、幼い子供たちにとっては、たわわに実るくわごが何よりのおやつだった。黒く熟れるのを待ちかねて、毎日くわごの色ぐあいを見るのも子供たちの楽しみの一つだったし、熟れたら素早く、他の者に先がけて取ってしまうのも、ちょっぴり真剣な遊びだった。
伊達の蚕種業を営む家に生まれて育った高夫にとって、桑はふるさとの木であった。幼い頃の思い出と、伊達の緑の大気を呼びおこしてくれる大切な木であったのだろう。
くわごの時期、高夫は、国会に行く前にいつもくわごを一粒、口に含んで出かけて行った。
庭のすみには、これも高夫が自分で植えたうこぎの木があった。春、うこぎの新芽が萌え出すと、「うこぎごはんが食べたいなぁ」と高夫がいう。嫁のまゆみは何のことかわからない。高夫は自分でうこぎを摘んで、塩でもみ「こうするんだよ」よ、炊きたてのご飯に混ぜた。緑が美しく、香ばしい“うこぎごはん”のでき上り。うこぎの味噌汁を添えて高夫の好物らしい春の膳であった。-伊達には、どの家にも生垣にうこぎが植えてあったという。春になると、うこぎごはんをよく食べた。その家その家の味があり、高夫も母の味をたどっていた。―秋はくわご、春はうこぎ。都会の小さな庭に、高夫を大きなふるさと・伊達があった。
主を失った桑の木は、ことしもまたたくさんのくわごを実らせるだろうか。

二度と再び、母国の英霊を作ってはならない。―亀岡高夫の生涯―
亀岡高夫は、伊達郡桑折町伊達崎に生まれた。生家は養蚕の盛んな伊達一帯に、蚕の卵を提供する蚕種業を営んでいた。十一人きょうだいの末子として、家族の愛情を集め、伊達のゆたかな自然の中でのびのびと幼年時代をすごしたが、まもなく押し寄せてきた昭和恐慌で、養蚕農家は次々とつぶれ、高夫の生家もその波をかぶって傾いた。
当時、保原中学に通い、熱心に勉学に打ちこんでいた高夫は、家の事情を考えて大学への進学を断念。昭和二十年、陸軍士官学校に入学する。この年の七月、日本・中国の両軍は全面的な戦闘に入り、日中戦争は激化の一途をたどり始める。昭和十五年、陸軍士官学校を卒業した高夫は、歩兵連隊に配属された。翌十六年、日本の真珠湾奇襲によって太平洋戦争が開戦。日本軍は先へ先へと前進をつづけ、香港、シンガポール、ラバウルを相次いで占領、国中が勝利の幻想にわき返っていた。昭和十七年、日本軍は、ニューギニアラバウルからさらに敵地に進出すること一千キロのガダルカナル島を占領した。東京から五千キロ近くも離れて、糸のように細くのびた日本軍の補給線の先端を突いて、八月、米軍が上陸、激しい戦闘が始まる。日本軍は次々と兵力を送りこんだが、それ以上の速度と量で米軍戦力は強化された。
高夫がガダルカナル島に、陸軍・亀岡中隊長として百人の部下と共に送られたのは、わずかに十歳の時であった。
陸・空・海底に死闘がくりひろげられた。しかし兵隊は、敵と戦うと同時に、ジャングル、スコール、デング熱、マラリアとも戦わなければならない。補給補が絶たれ、餓死する隊も相次いだ。こうして日本軍は壊滅した。
十七、八歳の若者たちで結成されていた亀岡隊も、高夫を含めて三人を残して全滅した。高夫自身もサソリに刺されて生死の境をさまよい、全身に九発の弾丸を浴びた。生還できたのが不思議である。
戦争中も、高夫が肌身離さず持っていた小さな手帳がある。そこには、ガダルカナル島で死んでいった若者たちの、命日と故郷が丹念に記してあった。終戦後、高夫がまっ先にしたことは、戦死した部下たちが、あれほど帰りたかった家、会いたかった家族を代わりに訪ねることだった。
激しい戦闘と地獄のようなジャングル、飢えの中で、まだ人生の緒についたばかりの部下たちを死なせてしまった。最後に母を呼びながら息絶えていった、童顔の残る面影がひとりひとり、高夫の胸に中に刻み込まれている。この悔恨と悲しみが、やがて高夫を動かすエネルギーとなっていった。
郷里・伊達崎にもどった高夫は、分家・亀岡正元の娘・秀子と結婚した。
ガダルカナルの劣悪な環境で無理を重ね、戦闘で全身九カ所に傷を負った高夫の身体は弱り切っていった。故郷で農業をやろうと思ってもどったが、農作業を続ける体力に自信を持てなかった高夫は、秀子と共に東京に出た。
終戦直後で物資が乏しい時期だったので、軍人だった高夫にも何とか行商でくらしを立てることができたが、まもなく高夫は結核にかかり、二年の闘病生活を余儀なくされた。当時はまだ死病と恐れられていた結核の魔の手からも、高夫は生還した。昭和二十三年のことである。
この頃、日本は戦後の復興が目覚ましく進んでいたが、東北・新潟など雪国の困窮はひどく、復興以前の、雪害との戦いの中で貧しさにあえいでいた。そこで、雪国のハンディキャップをとり除こうと、国会内に積雪寒冷地対策事務局が設けられ、東北・新潟の議員が中心になって活動を始めていた。その中のひとり、新潟出身の渡辺良夫代議士が、友人である高夫と事務局をつなぎ、高夫は局長として職務に就くことになった。
この時期に、高夫は田中角栄と出会う。高夫・二十七歳、田中角栄・三十九歳と、一まわりも年は違ったが、同じ雪国出身ということもあって、二人はよく気が合った。高夫は、この寒冷地対策の中で、しだいに政治に目ざめていった。
昭和三十五年、高夫は故郷・伊達から衆議院議員として立ち、初当選を果たした。昭和四十年には郵政政務次官、四十二年には内閣官房副長官、昭和五十五年、田名内閣では農林水産大臣を務める。
大臣就任と同時に待っていたのは、大冷害と台風だった。「農土の発展なくして国の発展はない」と訴えつづけていた高夫は、その対策に身を粉にして働きつづけた。食事も睡眠も満足にとらずに働く高夫に、秘書官は心配しながら付いていたら、高夫はある時、突然尋ねた。「君は何が楽しい?」―秘書官が返答につまっていると、高夫はほほ笑みながら言った。「僕は、こうして生きていることが楽しい。」
昭和五十九年六月、長く病床に伏せていた妻・秀子が亡くなった。長い間、陰で高夫を支え続け、高夫の心の支えでもあった秀子の死は大きかった。「これで見舞いに行く楽しみがなくなった…。」高夫はつぶやいて肩を落とした。
昭和六十年、高夫は永年在職議員として、宇野・海部両元総理と共に表彰を受けた。国会議員として、連続十回の当選を果たし、つねに「日本が中道を行くことができるためにどうしたらいいだろう。そのことを考えて努力していきたい。」と語って、日本と世界の平和を願い続けてきた。
妻を亡くしてから、自らも体調を崩してきていた高夫だったが、政治家としては決して自分に甘えず、病をおして前に踏み出す姿勢を崩すことはなかった。
日本の未来と平和を担う子供たちの教育に政治家も真剣にとりくまなければならないという目的のもとに、幼児教育懇談会を組織し、高夫亡き現在もその活動は続けられている。昭和六十三年には、地道で正確な調査のうえで、福島空港の国際空港化を誰よりも早く提言。日本人は世界の平和を考えられる国際人たれ、という高夫の思いが、この提言には込められている。
昭和六十四年一月七日、昭和天皇が崩御。重い風邪をおこして大喪の礼に参列した高夫はまもなく倒れ、同年三月十三日、六十九歳の若さでこの世を去った。
亡くなる一週間前、高夫は病床で偉民に語っている。「僕は、戦争で大勢の部下を死なせてしまった。命ある限り、その償いをする。二度と再び母国の英霊を作ってはならない。僕は、命ある限り、みんなのために働く。日本と世界の平和のために働く。」―父は、また元気になって、精一杯働けるようになる、と信じていたのだと偉民は思う。
ガダルカナルで死んでいった部下たちの命日を記した手帳は、長い歳月を経てなお、高夫の手元に大切に残されていた。この手帳が政治家としてひとのために働くことだけをよろこびとした、高夫の心の原点であり、行動の指針であったのだろう。
体はボロボロになっても、前に前に進もうとする高夫の心は、いつも世界の明日を見ていた。
「二度と再び、母国の英霊をつくってはならない」―高夫の願いを、私たちの誰ひとり忘れてはならない。