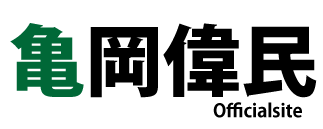スパルタ教育なんのその。俺は忙しい。―小学生時代―
一九五五年九月十日、四日市市に、元気な男の子が誕生した。小倉啓道、みき枝夫妻の二男坊・現在の亀岡偉民である。
ずっしりと重く、みるからに明るく、近い将来の腕白ぶりが容易に想像できるあかんぼうだった。二人の姉とはじめて弟を持った幼い兄の喜びはひとしおだった。
赤ん坊は偉民(よしたみ)と名付けられた。強い信念と大きな愛で、世の中のために役立つ民なれという、父と母の願いを込めた名が、のちの彼の歩む道を示唆している。
偉民が生まれてすぐ、一家は栃木県下都賀群国文町小金井に移った。
ここで母・みき枝は幼稚園を開いた。みき枝は幼い頃、子供のいない親戚に養女に入ったが、養父は当時、小山市で愛泉学園幼稚園を経営しており、地元で着実な幼児教育の足跡を残していた。みき枝にもその素質と意思が受け継がれ、小金井の愛泉学園幼稚園を創立、ここで幼児教育の基礎を築きはじめた。
父は、会社勤めをやめ、独立して農機具店を開いた。

幼稚園園長として、農機具店の経営者として、それぞれに新しい道を拓こうとする両親は、毎日戦争のように忙しかった。姉たちも兄も自分たちのことで精いっぱいで、偉民はいつもひとりぼっちだった。誰もかまってくれない。自分がやらなければ何も動かない。偉民は、ひとりでいることを自然に受け入れ、たくましく育っていった。
小学校の学芸会の日、ようやく時間をやりくりして出かけて行った母は、片びっこのくつ下をはいて、堂々と舞台に立っている偉民の姿を見て、笑いながら泣いた。
そんな少年にとって一番の楽しみは、週一回、母の幼稚園にやってくる祖父と過ごすひとときであった。あごひげを長く伸ばした祖父は、来るたびに偉民にいろいろな話をしてくれた。いま思えば、子供にとっては難解な、人生の真実にふれるような話もあったようだ。祖父のわきに座って話を聞くことがうれしかった。
偉民は祖父を「お話おじいちゃん」と呼んで慕った。お話おじいちゃんは、偉民にいろいろの本を与えた。少年は、無限に広い未知の世界があることを知りはじめた。わからないままに、偉民は本をむさぼり読んだ。読めない漢字、わからない語句をよけ、幼いながらも、自分の感性でわけ入っていく未知の世界は、すばらしく魅力的だった。偉民が少年時代に祖父から与えられた本―聖書の一節が書いてある「家の光」と国木田独歩は、ボロボロになっていまも残っている。
忙しい家族からひとりひとり残されるさびしさを、少年は“知”の世界に触れることでうめていったのかもしれない。やわらかな心と熱いほどの知的好奇心を持つ偉民を、お話おじいちゃんはこよなく愛した。

他の姉兄にはなく、偉民だけに天から与えられたそしつがあった。抜群の運動神経である。文武両道の精神を尊ぶ父母は、末っ子の偉民に望みをかけ、偉民に両親の理想とする教育をほどこす。
父は、厳しかった。まず、自宅すぐの前にある中学校のグランドを走って十周する。偉民はマッチ棒十本を持って走りはじめ、一周ごとに一本落とし、まちがいなく十本落として十周完走を証明しなければならない。一本ぐらいごまかしてしまおうかという思いがチRと頭をかすめることもあったが、ベンチに座った父は、新聞を広げながら、眼は息子を追っていた。グランド十周は、雨の日も風の日も続いた。
黙々と走る偉民、ベンチでそれを見守る父―言葉こそ交わさないが、ふだん仕事に忙殺されて息子をかまってやる暇もない父と、ひとりぼっちですごす子の、唯一の対話だったといえるかもしれない。
グランド十周のほかに、オルガンとピアノも習わされた。オルガンがいやで、窓から逃げ出し、母に追いかけまわされることもあった。
水彩と油絵もやった。小学五年になると、国体選手のコーチ付きで、みっちり剣道をやらされた。
「南無八幡大菩薩。成せば成る。成さねば成らぬ何事も」―毎日その書の前で正座させられ、大声で何度も読まされた。
持って生まれた体格と運動神経は、父母の鍛錬によってみがきがかかり、一方で貧欲に知の世界にわけ入っていく早熟さをみせる偉民は、大人にとって扱いにくい子供になる。小学四年のころから、彼はまわりにとっては手のつけられない”悪ガキ”になっていた。-先生のいうことはきかない・自分のペースは変えない・ケンカはしょっちゅう・授業はかきまわす・先生がぶんなぐってもいっこうにこたえない…クラス中がリーダー・偉民のもとに結集して、校内最悪の悪ガキクラスとなり、スポーツも成績も迷走しつづけて、先生たちの頭痛のタネになっていた。
偉民は。もどかしかった。
何かが内からあふれてくる。いいようのないエネルギーが自分をかり立てる。大人たちはそれを四角い小さな箱に閉じこめようとする。ああ、いやだ、いやだ
しかし、先生泣かせの悪ガキに、あるとき大きな転機が訪れる。
小学五年のとき、クラス替えがあり担任が変わった。斎藤ミキ先生という、母さんのような先生だった。悪ガキクラスは手ぐすねひいて先生を困らせるチャンスをうかがう。「先生、今日はお天気がいいから、授業やめて表でサッカーやろう!」偉民がもちかける。クラス中が先生の反応を待った。「さあ、怒るぞ、説教が来るぞ」―いままでの経験では、怒声かゲンコツが飛んだ。
ところが斎藤先生は違った。「しょうがない、みんなでサッカーをやろう!」―悪ガキ連中は虚を突かれた。一瞬の静寂のあと、クラスはわきかえった。「よーしサッカーだ!サッカーやるぞ」偉民はこのころ、サッカーに夢中になっていた。
偉民たちは、斎藤先生との出会いから変わっていった。子供たちを押さえつけず、小さな枠に閉じこめず、のびのびと解き放ってくれた。生きることがうれしくてたまらないという子供本来のエネルギーを、大切に見守ってくれた。
「何をやってもダメ」―学校中から鼻つまみだった悪ガキクラスは、みるみるうちに変貌した。
偉民をリーダーとして鉄のチームワークを誇り、成績もスポーツも群を抜いて伸びていった。偉民は、不思議な充足感と安らぎを覚えた。ようやく自分をわかってくれるひとに出会えたという…。
偉民はよく本を読んだ。
学校で暴れまわっている姿は想像もつかないが、お話おじいちゃんを待ちわびた幼い頃から、変わらずに本をよみつづけた。文学全集を片っぱしから読破する。聖書の語句や仏教やキリスト教に関する記述が出てくると、これは何だろうと思う。欧米の文芸は、キリスト教の文化がわからなければ理解しきれない、と感じる。そのためには聖書を読まなければならない―彼は旧約聖書も読破する。小学校高学年の少年には難解な対象ではあっても、偉民は精いっぱい知の世界を切り拓いていた。
彼はまた、音楽を愛した。かんかんに日の照る庭の芝生の上にステレオを出し、ボリュームをいっぱいにあげてクラシックに聞き入った。ときにその中で本を読んだ。
家にいればひとりぼっちでいなければならない空白を、偉民は少年なりに、充実した自分の時間にしていた。
学校一の暴れん坊と、読書好きの少年…相反する二面が、偉民の中ではすごく自然に融合していた。何だかわからないもどかしさ、内から沸き上がってくる苛立ち、行き場をさがしてさまようエネルギーを、偉民はいつも自分の内に感じていた。
やがて悪ガキ偉民は、自宅から目と鼻の先の国分寺中学に入学する。

野球と、親友がかけがえのない宝だった。-野球に出会った中学時代―
偉民が入学した町立国分寺中学校は、栃木県ナンバーワンの野球名門校として知られていた。
小学校時代、サッカーに熱中していた偉民だったが、ある時テレビで見た早慶戦に感動し、すっかり野球に魅せられていた。加えて、小学校からの悪ガキ仲間で一番の友人だった早乙女永に「野球やらないか」と誘われる。偉民が慕っているお話おじいちゃんの息子・森巖も、早くから偉民の素質を見抜き彼の顔を見るたびに「野球をやれ!」とすすめていた。偉民は、中学に入るとすぐ、一も二もなく野球部を選んだ。
野球は、偉民の心をすっぽりとその大きなグローブにおさめてしまった。
偉民は、たちまち野球にのめり込んでいった。
野球がおもしろくてたまらない。好きで好きでたまらない。授業中も、野球のことで頭がいっぱいだった。神様のいたずらか、思いやりか、偉民の隣の席は、ピッチャーの吉田修一だったからたまらない。ふたりは何度となく、教室の壁ぎわ沿いのはめ戸を外して授業を抜け出しては野球の練習をした。どうせすぐ先生にみつかってなぐられるのに、わかっていても心は野球に飛んでいく。ふたりは、できることなら一日中野球をやっていたかった。野球以外のことに費やす時間が惜しくてたまらなかった。
野球部の練習は厳しかった。
栃木県中学野球のボスのいわれた高橋監督のもと、偉民は身も心も野球に打ち込む毎日を送った。練習もきつかったが、先輩のしごきも半端なものではなかった。正座したひざの間にバットをはさんで正座させられ、そのバッドの上に先輩がどかっと乗る。-そんなことにも偉民はへこたれなかった。
野球が好きでたまらない、その気持ちがどんなしごきの辛さもはねのけていった。
偉民は、持ち前の素質と負けん気で頭角を現していった。お話おじいちゃんも、そんな偉民をあたたかく見守った。
国分寺中と常に張り合い、夏の県大会では優勝した強豪・栃木東中のピッチャーが、偉民は苦手だった。どうしてか、いつも彼の球は打てない。秋の大会でまた栃木東と戦うとき、おじいちゃんは偉民のために“魔法のこより”を作ってくれた。「これをバットのグリップにしばってみろ。かならず打てるから。」
-本当にこよりは偉民に力を与えた。偉民のバットは快音を立てて、宿敵の球をたたいた。そして、国分寺中は、秋の大会で優勝する。
偉民は、言葉では言い表せない感動を覚えた。不思議でならなかった。何か大きな力が自分を動かした。打てた。勝てた。-偉民は、この優勝をステップに、さらに力をつけ、もっと深く野球を愛していく。
野球に明け暮れた偉民の心の中に、あたたかで確かな存在となって入ってきた友がいた。小学時代からの悪ガキ仲間・早乙女永である。
彼は、スポーツ万能、成績も優秀で、何をやらせてもみんなをうならせる学校のスーパースターだった。偉民と早乙女は、なぜか気が合った。
小学時代、ふたりはサッカーに熱中した。偉民がアシストすれば、早乙女が必ず決める。ひと言も声をかけあうこともなく、ふたりは一つの心を共有しあうかのように、みごとなコンビネーションでグランドを暴れまわった。
仲間うちの試合では飽き足らなくなったふたりは、「中学生と試合をさせてほしい」と先生に頼みこんだ。二人とも小学生ながら一六〇センチをゆうに越える長身としっかりした体をしており、体格のうえでも中学生にひけをとらなかった。願いがかなって、中学校チームと偉民・早乙女チームが戦ったが、優劣つけ難く引き分けとなった。ふたりの技量と情熱はその頃すでに小学生の域をはるかに越えていた。
中学校に入ると、早乙女は毎晩、偉民の家にやってきて勉強した。ときにはそのまま偉民の部屋に泊り込み、翌朝五時ごろ家に帰ってから学校に来ていた。たとえ偉民が留守でも、早乙女はやってきて、ひとりで偉民の部屋ですごして帰っていった。
彼の父親は職人のようだったが、家庭に何か複雑な問題があるらしかった。早乙女は何も語らず、偉民も何も聞こうとしなかった。
ふたりには、そんなことはどうでもよかった。いっしょに勉強したり本を読んだりして過ごす時間が大切だった。早乙女はスポーツでやや偉民よりすぐれていた。偉民は勉強で少し早乙女に勝っていた。ふたりはお互いの足りない分を教え合い、補い合い、尊敬し合っていた。
当時若者の間で流行したサイモンのガーファンクルの「明日に架ける橋」を、ふたりは愛した。荒れ狂う川に架ける橋のように、僕は身を横たえよう、君のための橋になろうという歌詞が、一点くもりもない若い二人の心を表しているように思えた。ジュリー・ウォーレスの「男の世界」という曲もふたりは好きだった。少年から青年に成長しようとするふたりの心を曲に重ねて聞いていた。
偉民にも早乙女にも、お互いかけがえのない友だった。
自分たちがこれからどんな道に進んでいくのかわからないが、彼はきっと自分といっしょに歩んでくれる。自分の片腕になってくれるーと偉民は感じていた。何を言わなくても、早乙女も、そんな偉民の心がわかっていた。
中学卒業が、ふたりをそれぞれの道に分けた。偉民は野球一筋にかけて作新学院を選び、早乙女はサッカーの夢を追って宇都宮工業高校に行った。
それぞれの、希望に満ちた出発だったが、これがふたりを永遠に分かつ最初の分岐点となった。